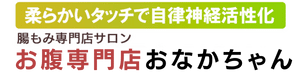
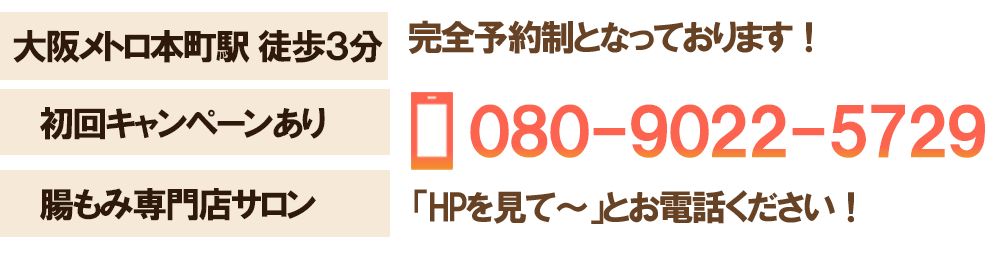
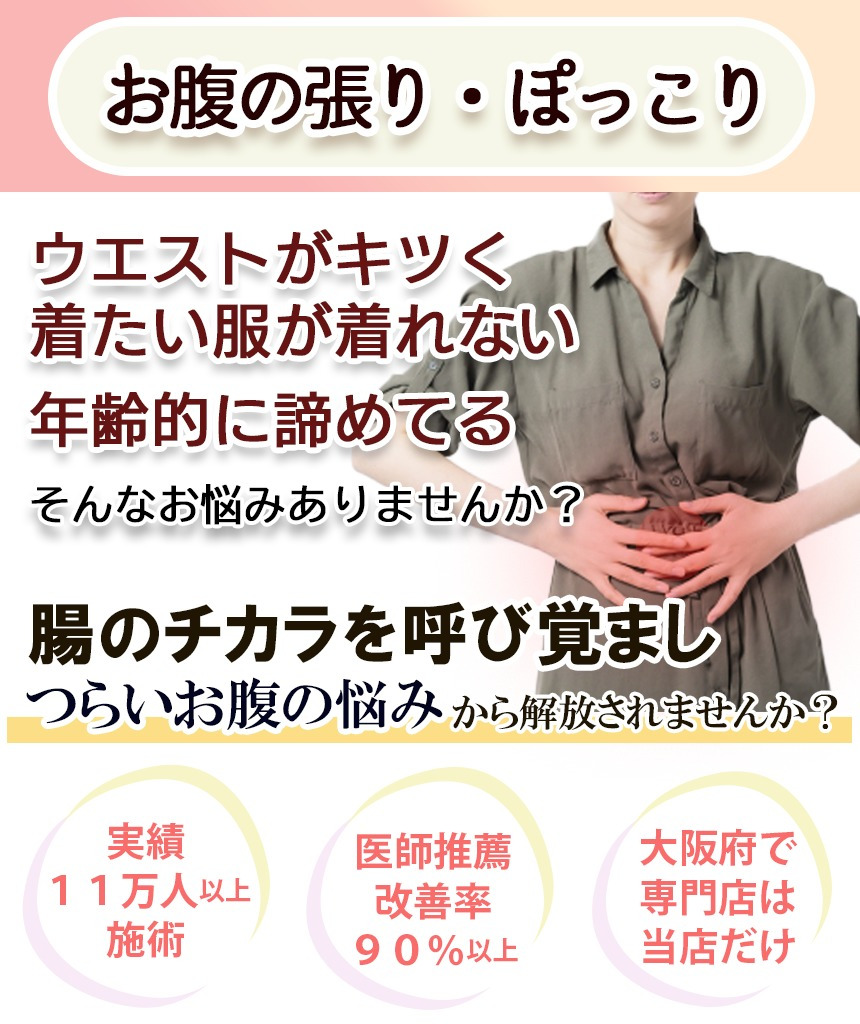


お腹の張りやぽっこりお腹には様々な原因があります。
お腹の中には腸が大半の体積を占めています。
では腸に何かの原因が起こっているためにお腹が張ってきたり、ぽっこりしてしまったりという現象が起こってしまうのか?
まず知って頂きたいのは 腸は自律神経によって働きや動きを調整されているという事。
この自律神経の交感神経(興奮する神経)と副交感神経(リラックスする神経)の2つがバランスで成り立ってます。
腸は副交感神経が働いているときに腸が収縮し食べ物や液体やガスを出口へ押し出し出します。
腸は交感神経優位のときは拡張して動きが止まっているためお腹が張ってきたりぽっこりしてきたりといった事が起こってきます。
お腹が張っているときは交感神経が優位になっていると言う事。
病気によりお腹が張ってくる事がありますが病気と診断されずにお腹が張ってくる場合は主に上記の事が原因となります。
早食い、良く噛まない、炭酸ガスの入っている飲み物を飲むのが原因です。
心因性の場合は緊張したりストレスがかかると空気を異常に飲み込んでしまう呑気症や自律神経の機能異常があります。
最近多く見られる過敏性腸症候群(IBS)による腹部膨満感や腹痛の原因もこれにあたります。 腸内ガス産生の過剰は腸内細菌叢の変化で悪玉菌が増えてくると、異常発酵により腐敗ガスが発生します。
また、繊維質の多い食事や糖質を多く含む食べ物はガスを増やしやすく、吸収不良や腸内菌叢の変化によって過剰なガスが発生します。
消化管の運動機能が低下すると、腸内にたまったガスが排泄されずに腹部膨満感がおこります。
便秘や過敏性腸症候群がこの状態です。
その他に、腸閉塞では、腸内容物と共にガスも排泄できません。
腸粘膜の炎症や循環障害では、ガスが身体に吸収されて呼気として排泄できませんので腹部膨満感がおこります。
女性は生理前から必ずと言っていいほど、お腹が張ってきます。
これはプロスタグランジン(子宮を収縮、生理痛の原因物質)があることで、痛みがあると常に緊張状態になり上記にある交感神経優位の状態になることでよりお腹が張り子宮の内膜を排出する手助けにもなったりします。
東洋医学では 胸脇苦満(きょうきょうくまん) とは ・胸と脇、つまり前胸部と両わきの下にある肋骨に覆われた部分を指します。
【 なりやすい人】
・ストレスにより「肝」の機能が低下して気が滞り(うっ滞)の状態
・病院で検査しても異常なしと診断されやすい人
・自律神経失調症や抑うつ状態と診断された人
【出やすい症状 】
・この部分に圧迫感や変な感じがあり、胸苦しくスッキリしない状態
・胃の部分や横腹あたりが、何となく張って苦しい
・ブラジャーや下着をつけると、苦しい
・ネクタイをきっちり締めたくない
・一度にたくさん食べることができない
自分の体の異変や辛さに対してのセンサーが鈍くなっています。なので相当酷い状態にならないと自分の不調がわかりません。
【 なりやすい人】
・ビール腹のお腹は硬く張っているパンパンのお腹“太鼓のようなお腹”
・おへそを中心にお腹が硬く盛り上がっている
・硬く大きなお腹の中には、気や血が滞り、老廃物が詰まっていると考えられる、ビールのお腹になりやすい人
・食欲旺盛で肉や油ものなどの美味しいものが大好き
・お酒を飲んで夜更かしをする
・無理が利く社長タイプで不摂生を続けているのにも関わらず普段は風邪を引かないような人ですが健康的に一番危険なタイプです。
【出やすい症状 】
・メタボリックシンドローム
・高血圧
・高脂血症
・痛風
・便秘
・痔
・皮膚病など
たるんでるぽっこりお腹は東洋医学では虚満と言いお腹はブヨブヨした力のない感じのお腹“カエルのお腹”仰向けに寝ると柔らかく、ダラリと横に垂れ下がるような感じです。
お腹を引き締める力である“気”が不足してることで起こる。
【 なりやすい人】
・たるんでるぽっこりお腹になりやすい人
・甘いものや果実、冷たいものが大好き
・女性は妊娠線が目立ってる人
・出産後に太ったままで戻らない人
・出産という一大イベントで気を消耗したことで引き締める力が無くなり、ダラリと太ったままの状態。
【出やすい症状】
・筋肉が少なくブヨブヨした感じになる
・汗をかきやすい
・産後に太ったまま
・暑がりで寒がり
・関節痛など
【なりやすい人】
・へその下の辺りの所に力がなく、押すとフニャフニャ
・冷たい感じがしたり、色がくすんでいたり、皮膚が硬くシワがある
・腎の気が不足している状態
・生命のエネルギーやパワーが不足
※腎の気は先天の気(生まれる時に親からもらったもの。
先天的に持っている成長・発育のためのエネルギーなど)と後天の気(飲食物が消化器で消化吸収されて補充されるもの)とが合わさってできています。
※生まれ持った先天の気に日々、後天の気が補充されて腎の気となり下腹部に蓄えられている。
下腹部がフニャフニャになりやすい人
・冷え(一番の腎の大敵!)
・寝不足 ・性行為が多い
・過労
・ストレス
・暴飲暴食 出やすい症状 ・耳の症状(耳鳴りなど)
・精力減退
・排尿困難
・失禁
・便秘
・更年期障害
・髪(薄い、抜けやすい、細い、白髪)
・不妊
・骨粗鬆症
・腰痛
・膝痛
・冷えやすくなるなど 日常で気をつけること(養生)
・腎の気を損んわないようにする
・過度の性行為 ・冷えないようにする
・塩分の取りすぎた添加物の多い食事を控える
・睡眠不足や過労
【なりやすい人】
・お腹がフニャフニャ(小腹不仁)の逆
・へその下の辺りの所を押すと硬く突っ張っている
・冷たい感じがしたり、色がくすんでいたり、皮膚が硬くシワがある
・腎の気が不足している状態 ・生命のエネルギーやパワーが不足している
※腎の気とは先天の気(生まれる時に親からもらったもの。
先天的に持っている成長・発育のためのエネルギーなど)と後天の気(飲食物が消化器で消化吸収されて補充されるもの)とが合わさってできています。
※生まれ持った先天の気に日々、後天の気が補充されて腎の気となり下腹部に蓄えられている。
・冷え(一番の腎の大敵!)
・寝不足
・性行為が多い
・過労
・ストレス
・暴飲暴食 出やすい症状
・耳の症状(耳鳴りなど)
・精力減退
・排尿困難
・失禁
・便秘
・更年期障害
・髪(薄い、抜けやすい、細い、白髪)
・不妊
・骨粗鬆症
・腰痛
・膝痛
・冷えやすくなるなど
東洋医学では、体のどこかが突っ張ったり硬くなっているのは、どこか弱い所を守ろうとしている反応です。
その状態が続くと体は疲れてしまいます。
腹直筋が緊張している場合、その内側にある胃腸や内臓が弱っていることが多いです。
緊張は左右ともになってる場合もあるが、片側の実の事もあります。
【腹直筋がカチカチのお腹になりやすい人】
・ストレスや怒りの感情に弱い
・ストレスで食べ過ぎたり食欲にムラ
・東洋医学では肝は筋肉の“腱”の部分と関係し脾は筋肉の”肉“の部分と関係
・肝と脾は関りが深く、肝の勢いが強すぎると脾が上手く働かない
例で言うと、イライラして胃が痛くなるのは、怒り(イライラをカンカンしてるとも言いますが、このカンカンは肝臓の肝です)のために肝の働きが亢進しすぎている時に起こる現象です。
消化器に何らかの異常が発生すると、の上の危険信号が出され体の防御反応が起こります。
・心下痞(しんかひ)とは危険信号を感じ取った状態
・心下痞硬(しんかひこう)は腹直筋が硬くつっぱって、お腹の内部を守ろうとしている状態
・初期段階で、原因を改善すれば自然と消えますが、改善しないままだと防衛反応が強くなり症状がエスカレート
【みぞおちがみぞおちがつかえたり、みぞおちが硬いお腹になりやすい人】
・食べ過ぎ
・肉や油(脂)の多いものを食べる
・甘いものを食べる
・冷たいものを食べる
・よく噛まない
・早食い
・食べてすぐに寝る
・精神的ストレス 出やすい症状
・食欲不振
・吐き気
・げっぷ
・胃膨満感
・つかえ
・不安感
・イライラ
・うつ症状
・自律神経失調症
・不安神経症
・ストレス性障害
・みぞおちを指先で軽く叩くとチャポチャポと音がする
・何らかの原因で胃腸の働きが悪くなって余分な水分が胃に溜まり、滞ってる状態
普通は胃に溜まることは無いがカラダの水はけが悪いと、いつまでも胃に水が溜まり、胃の不快感や吐き気などの原因になることがあります。
【胃内停水(いないていすい)のお腹になりやすい人】
胃下垂の人に起きやすい症状。
・胃の内容物を腸へ送りだす機能が低下し、胃の中に溜まった水と、ある程度の空気があると、胃の中でチャポチャポと鳴る。
食後より食前の方がわかりやすい。
【出やすい症状】
・消化不良
・下痢
酷くなるとめまいや吐き気、精神不安につながります。
お腹に力が入らず、触るとえんぴつの芯が入ってるような感じの時は正中芯。
へそ上とへそ下の両方に見られるものとへそ上かへそ下だけに見られるものとがあります。
へそ中心にお腹の真ん中のみぞおちからへその下に少し圧を加え、左右に指を動かしながら探ってみると、えんぴつの芯が入ってるかの様な感触があります。
下腹部がフニャフニャの存在をより確かなものとする症候。
【お腹に力が入らない人のお腹になりやすい人】
・胃腸の機能がとても弱っている。
江戸時代の医書には「脾胃の虚は中かんより以下臍のあたりまで任脈通りに箸を伏せたる如く筋立つものなり、難治なり、中焦を補う薬なり」とあります。
【出やすい症状】
・正中芯(せいちゅうしん)が出てくるのは、周りの筋肉が弾力を無くしてグニャリとなり、やせて皮下脂肪も薄くなっています。
・体が相当弱っている状態です。
現代語でへそ上の正中芯は胃腸が弱く、病気も治りにくい。
お血とは ・「お」には滞るという意味があります。
通常ならばスムーズなはずの血の流れが滞っている状態です。
お血は腹部に症状が現れやすく、主に下腹部に出ます。
圧痛点(押すと痛いポイント)がへその斜め左下にある場合と右下にある場合とがあり、慢性化しているとお腹の両側に反応が出ることも多い。
【お血のお腹になりやすい人(原因は様々)】
・飲食不節(食べ過ぎによる肉や脂、砂糖など)
・喫煙
・運動不足
・ストレス
・外傷
・脱水
・冷え、冷房
・慢性病
・月経、出産、閉経
・遺伝 出やすい症状
・皮膚の色がどす黒くなる。(シミやくすみも含む)
・月経痛や月経不順、場合によっては卵巣嚢腫や子宮筋腫
・男性だと前立腺肥大
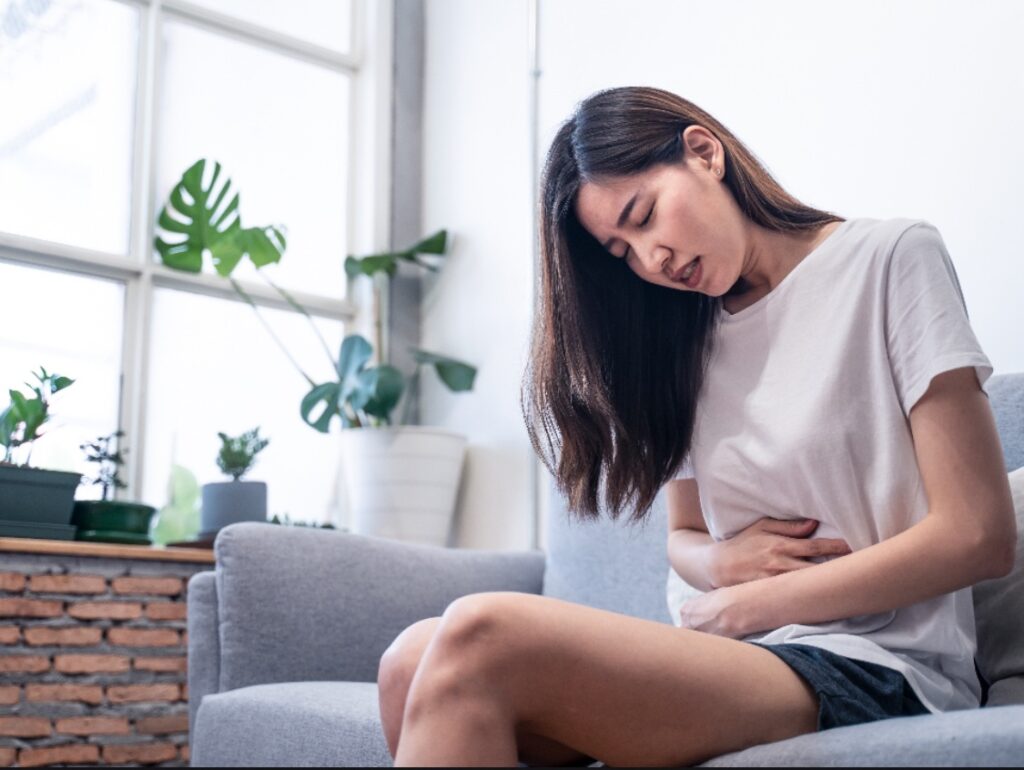
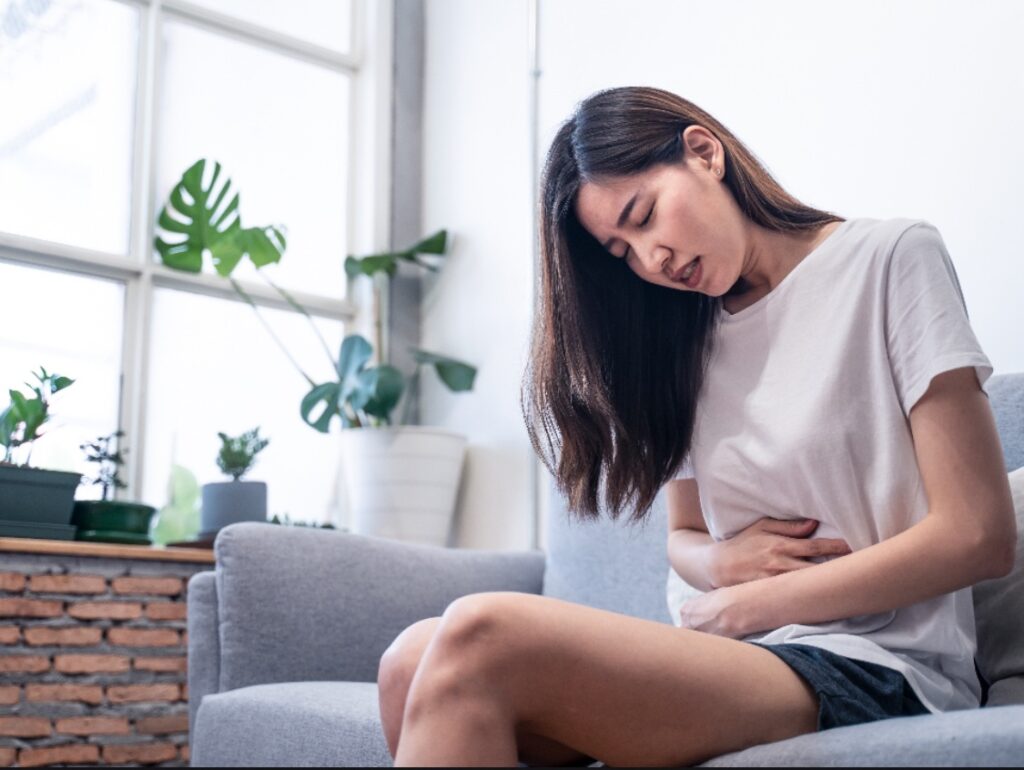
お腹の張りやぽっこりお腹が続くと 自律神経の調整が上手くできない状況で興奮する神経であるら交感神経優位の状態が続いている可能性あります。
体自身のメリハリができない状況です。
交感神経優位が続いていると胃腸や内臓の働きは低下し胃腸や内臓への血流量も低下するためお腹が冷え胃腸や内臓も冷える事で胃腸やその周りにある膀胱や子宮などに影響を及ぼします。


お腹の張りやぽっこりお腹の状態に合う東洋医学の鍼灸で使われているツボを刺激するのと同時に腸もみで施術を行います。
腸の働きをコントロールしている自律神経を腸からアプローチして自律神経の中枢である視床下部にアプローチします。
腸の動きが出てきて柔らかく収縮している状態が確認できたら副交感神経優位になっているため胃腸の血流量は増加し腸の動きがよくなります。
そうなると胃腸は収縮した状態になるためお腹の中の体積が小さくなる事で風船みたいに膨らんでいたお腹のぽっこりは小さくなりお腹の張り感も柔らかくなります。